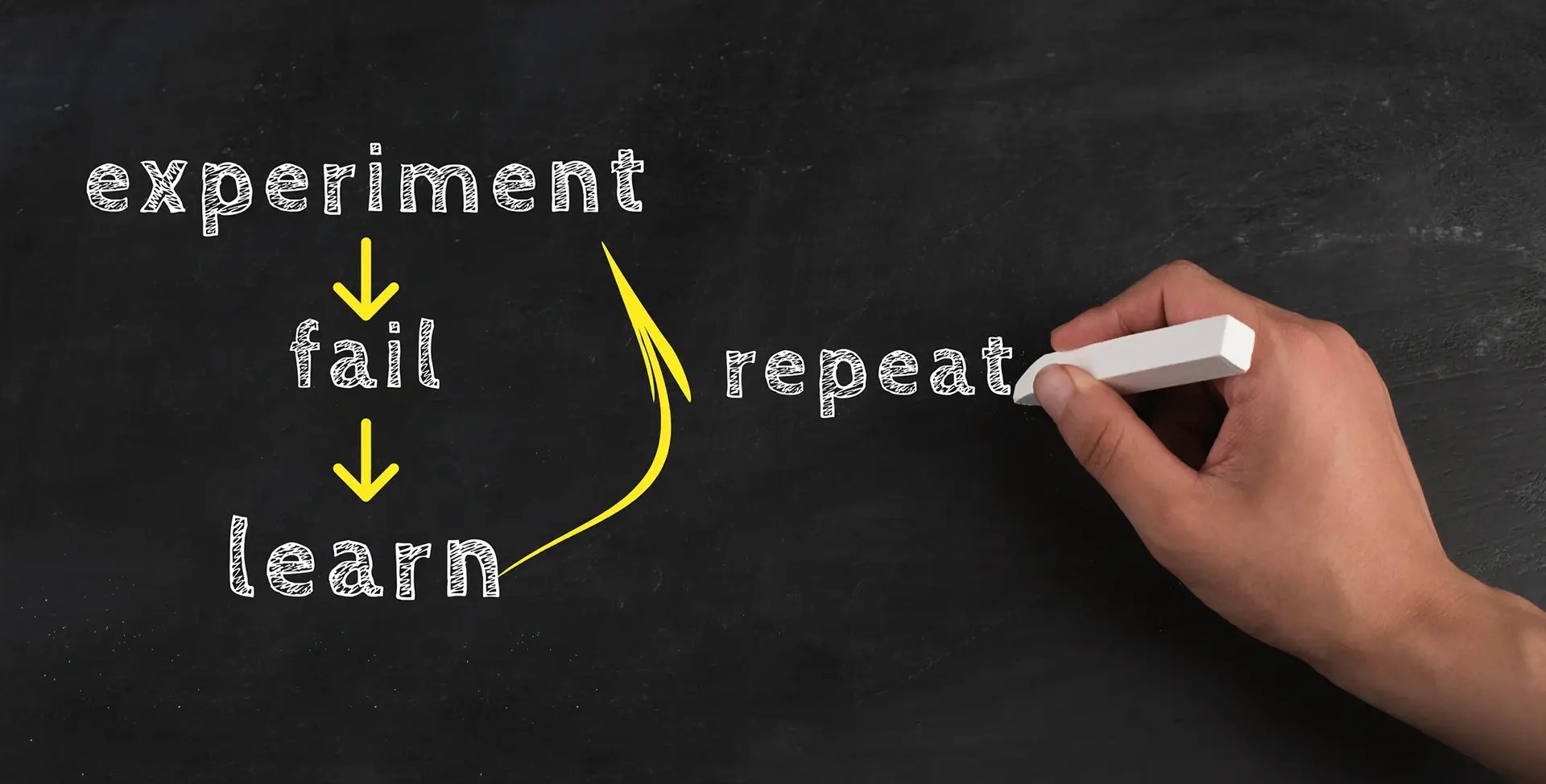失敗から学ぶ会社でのギフトコード活用術【5つのチェックポイント】
企業がマーケティングのキャンペーンや従業員向けの福利厚生としてギフトコードを採用する際に、担当者は「失敗したらどうしよう」という不安に直面しやすいです。予算や期限が限られているのに、ギフトコードの選定を誤るとスケジュールの遅れや施策の効果が十分に得られない結果になりかねません。
そこで、本記事では多くの企業に対してギフトコードの導入をサポートしてきた知見をもとに、「失敗しないためのギフトコード活用術」を徹底解説します。
景品選定で起きやすい3つの失敗
企業でギフトコードなどの景品を選ぶ際に、よくある失敗は以下の3点です。
これらに気をつけないと、無駄なコストの発生や施策の効果が十分に得られなくなってしまう恐れがあるため、注意が必要です。
対象者と景品のミスマッチ
受け取り対象者のニーズに合わない景品を選ぶと、効果が低減してしまいます。例えば、若年層向けのキャンペーン施策に「百貨店のギフトコード」を配布した場合、若年層の百貨店利用頻度が低い場合は、受け取り手の関心が薄くキャンペーン施策の反応率が低下する可能性があります。
稟議や発注手続きのトラブルで施策が遅れる
ギフトコードを購入する上で必要な社内の稟議申請や発注手続き、支払い方法などの流れを事前に把握していない場合、社内決裁に時間がかかり、ギフトコードの手配や配布が遅延する可能性があります。その結果、施策の開始時期が後ろ倒しになるなど、実行スケジュールに影響を及ぼす恐れがあります。
配布後の成果指標を決めていない
ギフトコードの配布を含むキャンペーン施策を実施する際、あらかじめ成果指標(KPI)を定義していない場合、施策効果の有効性を客観的に評価することができません。たとえば、「お問い合わせ数」「成約数」「キャンペーンの参加率」など、目的に応じた指標を事前に設定し、定量的な効果検証が実施できるようにしておくことが重要です。

ギフトコード活用の失敗事例
次に、実際によくあるギフトコード導入の失敗事例をご紹介します。
リード獲得には成功したが、成約に繋がらなかった事例
あるBtoBソフトウェアベンダーは、サービス資料のダウンロード特典として1,000円分のギフトコードを進呈するキャンペーンを実施。その結果、従来のオンライン広告と比較して30〜50%ほどのCPAでリードを獲得し、短期的なリード数の拡大には大きく寄与したものの、特典の受け取りだけを目的とするダウンロードが急増し、商談化率・成約率は伸び悩んだという失敗事例があります。
このような施策を成功させるには、
- 配布対象をセグメントで絞る
- 資料請求後にスコアリングや追加アンケートで関心度を可視化する
- キャンペーン期間を限定し、インセンティブの乱用を防ぐ
といった運用設計が必要です。
ギフトコードでリード数を拡大させつつ、成約率とのバランスまで見据えた計画をしていきましょう。
請求書払いができず、施策が後ろ倒しになった事例
四半期ごとのお問い合わせ数をKPIとしてギフトコードによるキャンペーン施策を企画。しかし、請求書払いに対応していないことがわかり、支払い方法の調整に時間がかかることに。その結果、キャンペーンの開始が2週間遅れ、季節性のある施策だったことも影響し、想定していた効果が得られず、KPIが未達成になった、といった事例があります。
マーケティングの現場ではスピードが求められることが多いため、ギフトコードを発注する際は、事前に発注方法や支払い方法を確認し、社内稟議を円滑に進められるサービスを選定することが重要です。また、万一の遅延に備えて余裕を持ったスケジュール管理も大切です。
失敗を防ぐ5つのチェックポイント
企業が景品としてギフトコードを導入する際によくある失敗を防ぐためには、以下の5つのチェックポイントを抑えることが重要です。
利用シーンに合わせたギフトコードを選ぶ
受取後のギフトコード利用シーンや対象者のニーズ/価値観に適したブランドのギフトコードを選ぶことで、対象者の興味・関心が高まり施策効果の最大化が期待できます。
例えば、個人顧客向け×若年層への謝礼の場合、『コンビニで利用できるギフトコード』がおすすめです。
コンビニで利用できるギフトコードは全国どこでも24時間使える「手軽さ」と、飲料・軽
食・日用品などすぐに役立つ商品との交換/決済に利用できるという即時性。
若年層の価値観として「タイパ(タイムパフォーマンス)」があり、「即時性」が対象者の持つ価値観とマッチします。
このように、「利用シーンで求められる価値」と「対象者の持つニーズ/価値感」に合わせて景品を選定することが、施策を成功させるポイントとなります。
期待する費用対効果(ROI)から必要枚数や単価を決める
ギフトコードを配布して対象者の満足度は向上したものの、事業成果として良い施策だったのかがわからないということにならないように施策が費用に見合った成果を上げているかどうかを判断するためにも、事前に期待する費用対効果(ROI)に基づいて目標数値を設定することが重要です。 例えば、過去のマーケティング施策では予算300万円を使用し1,000件の見込み顧客を獲得している場合は、1件の見込み顧客獲得コストとして3,000円かかっています。ギフトコードの有効性を加味し、2,000円のギフトコードを300万円分準備し、1,500件の見込み客を獲得した場合は、新規顧客獲得コストは1件あたり2,000円となり、費用対効果が改善されます。
過去の実績を分析して、ギフトコードの単価、発行枚数、想定される成果を整理し、予算内で効果を最大化できるような設計が重要です。
請求書・領収書の電子発行と審査サポートまでワンストップで対応できるサービスを選ぶ
企業向けギフトコードはブランド側による案件審査やクリエイティブ審査が必須となるため、注文から請求書・領収書発行までを“完全自動”で完了できるサービスはありません。
そのため、商品ブランド側への審査手続き、請求書・領収書の電子発行をワンストップで代行・サポートしてくれるサービスを利用することで事業部・マーケティング部・経理部などの業務負荷を抑えながら、スケジュール遅延のリスクも軽減できます。なお、LINEギフトなどは個人向けプラットフォームであり、法人の大量発注や請求書払いには対応していない点に注意が必要です。
可能な限り必要な数を発注する
多くのサービスでは原則ギフトコードの返却・払い戻しの対応ができないため、無駄のない数量を発注する必要があります。
景品表示法と業界ごとの規制を確認する
ギフトコードを景品やインセンティブとして配布する際は、景品表示法(景表法)の「一般懸賞」「共同懸賞」などに定められた上限額を超えないかを必ず確認しましょう。さらに、各業界には固有の規制が存在するため、自社の業種・業態に合わせたチェックも必要です。
また、2024年の改正により、ステルスマーケティングも規制対象となったため、告知方法にも注意が必要です。
例えば、保険会社は保険業法により換金性の高いインセンティブ提供が制限されており、ギフトコードを契約促進目的で配布することは認められていません。金融・医薬品・酒類などの分野でも、監督官庁や業界団体のガイドラインで金額・提供方法が細かく定められているケースがあります。
このように、「景表法」と「業界固有のルール」の両方を事前に確認し、違反リスクを回避できるスキームを設計することが、安全かつ効果的なギフトコード施策を実現する鍵となります。

知っておきたいギフトコードの種類
企業が活用できるギフトコードには複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。
代表的なカテゴリには、以下のようなものがあります。
- Visa eギフトなどの汎用決済型
- AmazonギフトカードのコードなどのECサイト型
- ポイント選択型(えらべるPayなど)
- コンビニ・カフェ系
- 百貨店・高級グルメ系
それぞれの特徴を理解しておくことで、活用の幅が広がります。
※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
Visa eギフトなどの汎用決済型
VisaやMastercardなど国際ブランドと提携した「汎用決済型」ギフトコードは利用可能店舗が幅広く、受け取った方の利便性が高いのが特徴です。様々な場面で使えるため、利用する対象や場面を限定したくない場合に有効です。Visa eギフトはオンラインVisa加盟店で利用することができるため、汎用性が高く、特定の利用シーンに縛られず幅広い対象に配布しやすい商品です。
※Visa eギフトはオンライン専用となり、オフライン店舗(実店舗)での利用不可
Amazonギフトカードのコードや楽天ポイントギフトなどのECサイト型
Amazonギフトカードのコードや楽天ポイントギフトなど「ECサイト型」のギフトコードは特定ECサイト内での決済に利用できる商品です。汎用決済型と同様、受け取った方の利便性が高い点が魅力です。キャンペーン景品やアンケート謝礼として定番で、消費者も使い慣れていて安心して活用しやすい点も利点です。
ユーザー選択型(えらべるPay、選べるe-GIFTなど)
事前に設定されている複数のサービスの中から受け取り手が好きなものを選んで受け取ることができる「ユーザー選択型」は、受け取った人が「欲しいものを自分で選べる」ため、ターゲットを限定させることなく幅広いニーズに答えられる柔軟性が利点です。
ユーザー選択型(えらべるPay、選べるe-GIFTなど)
事前に設定されている複数のサービスの中から受け取り手が好きなものを選んで受け取ることができる「ユーザー選択型」は、受け取った人が「欲しいものを自分で選べる」ため、ターゲットを限定させることなく幅広いニーズに答えられる柔軟性が利点です。
コンビニ・カフェ系
コンビニやカフェチェーン店で利用することができるギフトコードは日常的に利用しやすく、受け取りから利用までのハードルが低いため、満足度が高まりやすいのが特徴です。
百貨店・高級グルメ系
百貨店や高級グルメ系のギフトコードは「特別感」を演出でき、顧客ロイヤルティ向上や社員表彰などに適しています。一方で、利用可能なエリアや業態が限定される場合もあるため、事前に調べておくことをおすすめします。
失敗しないギフトコード導入まとめ
法人でギフトコードを導入する際には、以下のような失敗が起きやすい傾向があります:
- 対象者と景品のミスマッチ
- 稟議や発注手続きのトラブルによる施策遅延
- 配布後の成果指標(KPI)が未設定
こうした失敗を防ぐために、以下の5つのチェックポイントを押さえておくことが重要です。
ギフトコード導入前の5つのチェックポイント
- 1. 利用シーンに合わせたギフトコードを選定する
- 対象者の属性や用途に適したギフトコードを選びましょう。
- 2. 期待する投資対効果から必要な枚数・単価を算出する
- 過去施策と比較し、KPIをもとに予算配分を設計しましょう。
- 3. 審査サポートと電子請求書・領収書発行に対応したサービスを選ぶ
- 審査サポートと電子請求書・領収書発行に対応したサービスを選ぶ
発注・審査・納品・支払いまでのプロセスを業務負担を高めることなく進められるサービスを選定しましょう。
- 審査サポートと電子請求書・領収書発行に対応したサービスを選ぶ
- 4. 未使用ギフトコードの払い戻し条件・手数料を事前確認する
- 余剰分による無駄なコストを防ぐ仕組みがあるか確認しましょう。
- 5. 景品表示法と業界ごとの規制を確認する
- 景表法の上限額と、自社業界(保険業法など)で定められたインセンティブ制限を遵守できる運用体制を整えましょう。
これらのポイントを事前に確認・準備することで、マーケティング施策や社内インセンティブ施策において、ギフトコードを効果的かつスムーズに活用することができます。
法人企業向けのギフトコード(デジタル)・ギフトカード(紙製)の申込サービス「Kiigo for B2B」では、申込金額の大小に関わらず、細かなサポート対応で業務工数削減・効率化を促進します。お気軽にお問い合わせ・お見積り依頼ください。